「ご捺印(ご押印)してください」という敬語の使い方は間違い?
うっかり使ってしまいそうな表現ですが、このことば使いは間違いです。
「ご捺印」または「ご押印」ということばを使えば、相手を尊敬していることになります。
尊敬する相手に対し「~してください」といういい方は、ちょっと丁寧な命令口調に聞こえませんか。
「ご捺印(ご押印)お願いします」の方が相手を敬っている気持ちがつたわりますし、自然なことば使いだと思います。
あなたは、書類に、捺印(なついん)や押印(おういん)の印が必要なとき、どんな敬語表現の依頼文でお願いすればいいのか、迷うことってありませんか。
相手がお客様や上司であれば、
なおさら気を使ってしまいますよね。
そこで、ご捺印やご押印をお願いするとき、
どのような敬語が使われているのか調べました。
結果、なにも特別な文面でもなく、
ごく普通な敬語表現でよいということがわかりました。
下記例文が、ご参考になれば、嬉しいです。
ご捺印やご押印をお願いする文例
- ご署名、ご捺印の上、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。
- 内容をご確認いただき、ご署名ご捺印の上ご返送くださいますようお願い申し上げます。
- 誠にお手数ながら、同封の〇〇の箇所に印鑑をご押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
- 書類◯ページ目に、ご署名とご捺印をお願い申し上げます。
- 付箋を付しております箇所に付き、ご担当者様のご署名ご捺印をお願い申し上げます。
- 同意書の最後のページにあるお名前の横に、ご押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬語には、尊敬語、謙譲語、丁寧語などがあります。
印を押す行為を表す「捺印」「押印」に「ご」という接頭語を付けて、
目上の人を敬う「尊敬語」にし、
あとは普通に「お願いします」「お願い申し上げます」などとつづけるだけで
大丈夫なんです。
大切なお客様へ送るのであれば、
「ご署名、ご捺印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。」
でよいのではと思います。
「ご」が多くあるのは、くどすぎて、いんぎん無礼の印象を感じるという人もいるかもしれませんが、
私が受取人であったなら、悪い気はしません。
ただ、社内の上司にたいしてであれば、
- 署名捺印をお願いします。
で、十分敬語表現になっていると思います。
捺印と押印に違いはあるの?
捺印と押印、ことばは違っても同じ「印(印章)を押す」という行為を表しています。
「捺印」は古くから使われていました。
「押印」は新しく使われだした用語です。
じつは、「押印」が使われだしたのにはある理由がありました。
捺印でなく押印を使わないといけない?
捺印の「捺」は古くから使われていた漢字です。
それが、1946年に当用漢字(1850文字)が制定された際に、「捺」という漢字が当用漢字表に入らなかった。
そのために、「捺」を使った「捺印」という用語が公文書や法令などでは使われなくなりました。
代わりに使われるようになったのが、「押印」だったというわけです。
ただ、当用漢字表はあくまで「漢字使用の目安」にすぎず、一般社会では使い慣れた「捺印」を使い続ける人が多かったのです。
そのため、現在のように「捺印」「押印」の両方が入り混じって使われだしたのです。
平成22年11月30日には、改定された「常用漢字表」が告示されました。
内閣法制局長官 法令における漢字使用等について
この中で、「捺印」については、
”捺 印(用いない。「押印」を用いる。)”
(6ページ目、3行目)
と明記されたのですが、内閣告示にある常用漢字表は、あくまで「漢字使用の目安」であります。
各個人らが常用漢字表にない文字を従来からの文化、慣習などの理由から使ってもなにも問題はありません。
現に、「捺印」はビジネス社会においても、その市民権を確固たるものにしています。
捺印の読み方
捺印は、「なついん」と読みます。
押印は、「おういん」と読みます。
今は押印と表記するように求められており、公共の機関では「押印」に統一されています。
署名捺印と記名押印の違いとは
署名して印鑑を押すのを、署名捺印といいます。
記名して印鑑を押すのを、記名押印といいます。
当たり前のことですみません。汗
あと、捺印も押印も同じなのですから、
署名押印とか、記名捺印といっても、間違いだとまではいえません。
でも、聞きなれないことばであることは確かです。
決まった成句として、「署名捺印」「記名押印」と覚えればいいだけです。
署名とは
本人が、自筆で自分の氏名を書くことです。
筆跡、筆圧は人によって違いがあります。
署名であれば、筆跡鑑定で本人が書いたものかどうかを証明できます。
法的な効力をもたせることができます。
記名とは
署名以外の方法で、自分の氏名をかきしるすことです。
パソコンを使っての入力印刷や氏名印を押すなどの方法によります。
署名とは違い、氏名がしるされているだけで、本人の意思によるものか、
どうかまでは確認できません。
法的効力は捺印と押印どちらが上?
捺印する、押印する、という行為は、
印を押した書類の内容を認める意思表示をすることです。
その意思表示の強さを、法的証拠能力として順位をつけるならば、強い順から、
- 署名と捺印
- 署名のみ
- 記名と押印
- 記名のみ
となります。
なかでも、最強は、
署名捺印+印鑑証明書の組み合わせです。
「はんこ(印章)を押す」ことを、「印鑑を押す」と言い表すのが一般化されていますが、厳密に言うと「印鑑を押す」という言い方は間違いです。
おすすめ記事
[おすすめの記事はこちら]
>>印鑑の押し方でどの位置に押すかで迷ったことないですか?
>>印鑑とはんこの違いはなに?本当は「はんこを押す」が正しいんですね
>>捨印の訂正効力は絶対?訂正の範囲で争い勝目はあるのか?
>>「押印」の読み方は「おしいん」でいいのか?ダメなのか?
まとめ
- お客様に、捺印や押印をお願いする場合は、
「ご署名、ご捺印をお願い申し上げます」 - 社内で上司お願いするのであれば、
「押印をお願いします」

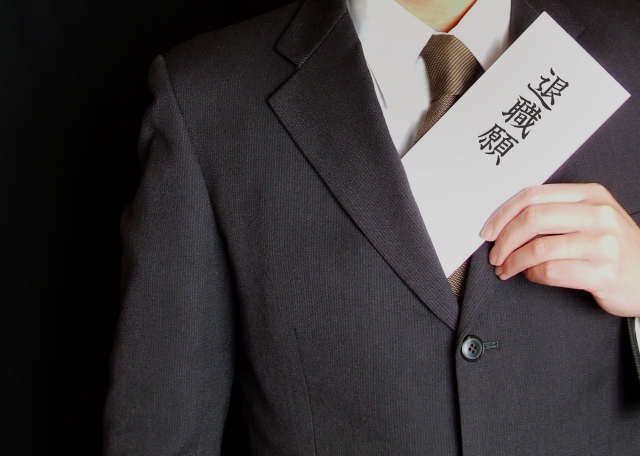

コメント