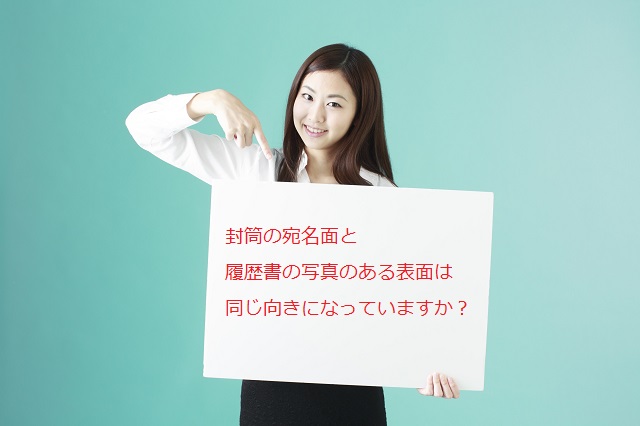「〇〇弱」とか「〇〇強」とか、弱や強を数字のうしろにつけて相手につたえることってありますよね。
正確ではないけど、おおよその数値を伝えたいときに使います。
たとえば、相手にある物の長さをたずねたときに、
「1メートル弱かな?」
あるいは
「1メートル強かな?」
という返事があったばあい、
おなじ1メートルに対して、「弱」と「強」ではどう違うのでしょうか。
「〇〇弱」「〇〇強」とはどういうこと?
- 1メートル弱とは、
本当の長さは、1メートルよりちょっと短い。
(端数を切り上げたから1メートルになる) - 1メートル強とは、
本当の長さは、1メートルよりちょっと長い。
(端数を切り捨てたから1メートルになる)。
という意味の表現方法です。
まぁ~「ちょっと」といわれても「どれくらいなんだ?」とつっこまれそうですが、
「〇〇弱」とか「〇〇強」とはこういうことだったんです。
「弱」の意味
「弱」とは、辞書の説明によれば、
- 「(数量を表す語について)数量が示した数値より少し少ないこと、示した数値が端数を切り上げたものであることを表わす。」
- 「ある数をある桁で切り上げたとき、その数に添えていう語」
となっています。
「強」の意味
「強」とは、辞書の説明によれば、
- 「(数量を表す語について)数量が示した数値より少し多いこと、また示した数値が端数を切り捨てたものであることを表わします」
- 「ある数のほかに切り捨てた端数があること」
端数とは、「数を、ある単位で切った場合の、あまりの数」です。
「弱」と「強」の使い方
たとえば、「99センチ3ミリ」の棒の長さは、「弱」「強」を使ってこういういい方ができます。
1メートル弱(端数の3ミリを切り上げる)。
99センチ強(端数の3ミリを切り捨てる)。
ただし、これらを聞いた人には端数の長さがどれくらいあったのかまでは分かりません。
端数がいくつだったら切り上げたり、切り捨ててもよいという決まりもないので、当人が勝手に決めているだけです。
「〇〇弱」「〇〇強」と教えられた人は、これまた勝手に端数の長さを想像するしかありません。
お互いにとって、じつにあいまいな表現方法です。
「弱」「強」使いわけの目安はどこ?
もともとが使い方にあいまいさがある「弱」「強」です。
そのため、表現のしかたに一定のルールを設けている企業もあるといいます。
有効数字が0.1桁きざみとなると
50.0 ⇒ 50.0
50.1,50.2,50.3 ⇒ 50強
50.4,50.5,50.6 ⇒ 50台半ば
50.7,50.8,50.9 ⇒ 51弱
50.0~50.9 ⇒ 50台
ただし、有効数字が一桁であれば、
50 ⇒ 50
51,52,53 ⇒ 50強
54,55,56 ⇒ 50台半ば
57,58,59 ⇒ 60弱
50~59 ⇒ 50台
となり、同じ50弱、50強、50台でも違ってきますので注意が必要です。
地震における「弱」「強」の使い方
その点、気象庁震度階級表の震度5と震度6については「弱」「強」をつける基準が決まっています。
震度
4.5以上5.0未満 震度5弱
5.0以上5.5未満 震度5強
5.5以上6.0未満 震度6弱
6.0以上6.5未満 震度6強
まとめ
- 「〇〇弱」は、正確には示した数値「〇〇」より少し少ないこと、また示した数値が端数を切り上げたものであることを表わします。
- 「〇〇強」は、正確には示した数値「〇〇」より少し多いこと、また示した数値が端数を切り捨てたものであることを表わします。