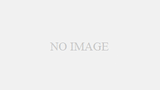「関わるとロクなことがない…」
そんな人、あなたの身の回りにもいませんか?
今回は「触らぬ神に祟りなし」という昔ながらのことわざを通して、人間関係のうまい距離の取り方について、じんさんが語っていきますよ。
「触らぬ神に祟りなし」の意味とは
このことわざ、一言でいえば「余計なことに関わらなければ、災難に巻き込まれないよ」という教えです。
余計なことに関わらなければ災いは避けられる
人間関係って、正しいことを言えば伝わるってもんじゃないんだよね。
特に相手がクセの強いタイプなら、下手に口を出したら、自分が損するだけってこともある。
まさに「触らぬ神に祟りなし」。巻き込まれないのが一番安全。
現代の“神様”は、身近な人の中にもいる
会社でもご近所でも、SNSでも、どこにでもいるよね。
怒らせると面倒な人。正論が通じない人。マイルール最優先の人。
こういう人に、正面から向き合うのは危険。適度な距離を保つのが、現代の処世術なのさ。
「触らぬ神に祟りなし」の由来と背景
この言葉、もともとは日本の昔の考え方からきているんだ。
日本古来の神への畏れと距離感
昔の人はね、神様のことを「ありがたい存在」でもあり、「怒らせたら怖い存在」でもあると考えていたんだよ。
よいことも悪いことも、神様の機嫌次第ってわけ。
“怒らせると怖い存在”としての神
だから、不用意に神様の領域に踏み込んだり、失礼なことをすると「祟りがある」と考えられてた。
その知恵が「触らぬ神に祟りなし」という言葉になったわけだね。
職場や家庭に潜む“祟る神”たち
さて、現代社会にも“神様”みたいな存在はいるものです。
正論が通じない人に対しては「距離」で対処
話せばわかる人ばかりじゃない。
中には「話すだけムダ」「注意すれば逆ギレ」「意見すれば逆恨み」って人もいる。
そんな相手には、論破よりスルー、注意より距離感が最適解だったりするんだな。
“正義感”で空回りした若手時代のじんさん
ワシも若いころ、やっちゃったことがあるよ。
30代の頃、新しく配属された営業部で、めちゃくちゃ横柄な上司がいたんだ。
会議で部下を怒鳴り散らすタイプでさ。
オレは「これはいかん!」と思って、正義感からこう言った。
「その言い方じゃ、誰もついてこないですよ」
……結果?
ものすごーく怒られたね。
しかもその後、仕事もやりづらくなって、周りの人までオレから距離を取り始めちゃった。
いやぁ~、あのとき学んだね。
「正しいことをいっても、相手を選ばないと火傷する」って。
まさに「触らぬ神に祟りなし」だったよ。
女性がイライラしているときは、逆に「声かけ」が効果的?
でもね、相手によっては「触らぬ神に祟りなし」が逆効果のこともある。
たとえば女性がイライラしているとき。
男の発想だと「そっとしとこう」が正解だと思いがちだけど、実は逆なんだよね。
女性の場合、「話を聞いてほしい」「気づいてほしい」って気持ちが強い。
だから無視すると、余計に怒りを買っちゃう。
こんなときは
「どうしたの?」
「何かあった?」
って一言、気遣いの言葉をかけてあげると、案外すーっと落ち着いてくれたりするから不思議だよ。
ことわざの似た表現や類語で見る“距離の美学”
このことわざに近い表現も、実は色々あるんだ。
似たことわざ:「君子危うきに近寄らず」「関わらぬが吉」
・君子危うきに近寄らず
・関わらぬが吉
・藪をつついて蛇を出す
どれも「危ないものには近づくな」って意味だね。
類語・同義語:無用な干渉を避ける言い回し色々
・余計なことは言わぬが花
・沈黙は金
・そっとしておくのが一番
…いやぁ、昔の人はホント、知恵がつまってるね。
英語で言うとどうなる?「触らぬ神に祟りなし」
この言葉、英語でいうとこんな表現が近いよ。
“Let sleeping dogs lie”が一番近い?
「Let sleeping dogs lie」=「寝ている犬を起こすな」
つまり「わざわざ問題を掘り起こすな」「そっとしとけ」って意味。
なかなか味のある言い回しでしょ?
まとめ:距離をとるのは冷たさじゃない
「触らぬ神に祟りなし」って言葉、冷たく感じるかもしれないけど、実は大人の知恵なんだよね。
相手によっては、声をかけた方がいい時もある。
でも基本は「深入りしない勇気」「巻き込まれない賢さ」が自分を守る。
人間関係に疲れたとき、ちょっと思い出してほしい。
ワシの人生訓のひとつさ。
です。